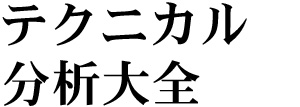1.DMIの表示構成
DMI (Directional movement Index) は、ワイルダーが考案した価格の変動幅に基づく市場分析です。
オシレータ系の順張り指標で、大きなトレンドを探り当てるために使われます。
前日の高値安値と、当日の高値安値との比較から、相場の強弱を読み取ろうとするもので、基本的には3つの線の位置関係から投資判断を行います。
なお、値動きの参照期間には通常14日間を採用します。
+DI (オレンジ線): 参照期間内の値動きのうちプラス方向の動きの割合
-DI (青線): 参照期間内の値動きのうちマイナス方向の動きの割合
ADX (緑線): +DIと-DIの乖離を示すDXの移動平均
▼日経225 (チャート:TradingView)

DIは、計算する際に、まずTRやDMといった指標が必要となります。
それらの計算式はここでは解説しませんが、要するに相場が日々上下する中で、上昇する値動きや下落する値動きが、それぞれどれくらいの割合を保っているのかを示したものとお考えください。
通常、相場が上昇傾向にあれば+DIは上昇し、相場が下落傾向にあれば-DIが上昇します。
ちなみに、DIの算出根拠となる+DM,-DMは、終値ではなく日々の高値・安値を用いて相場本来のボラティリティを測ろうとしている点が特徴の1つといえます。