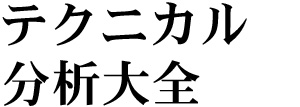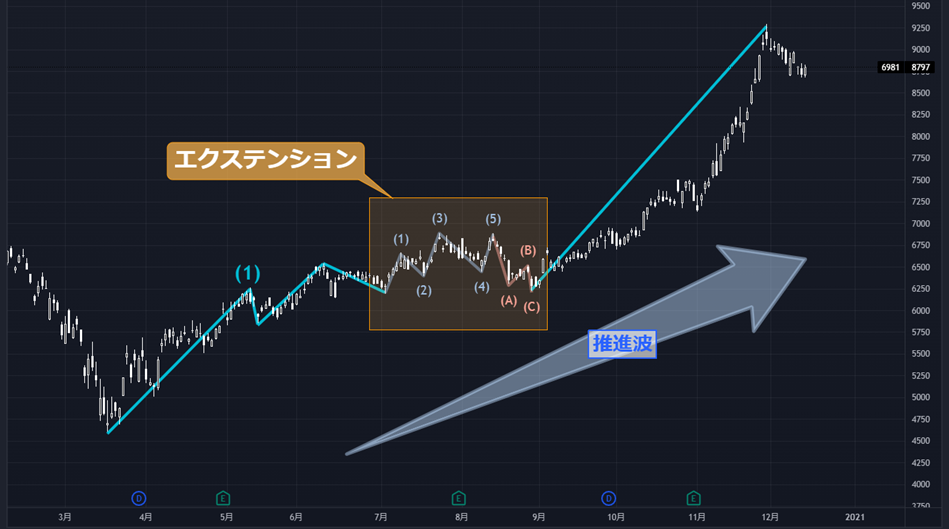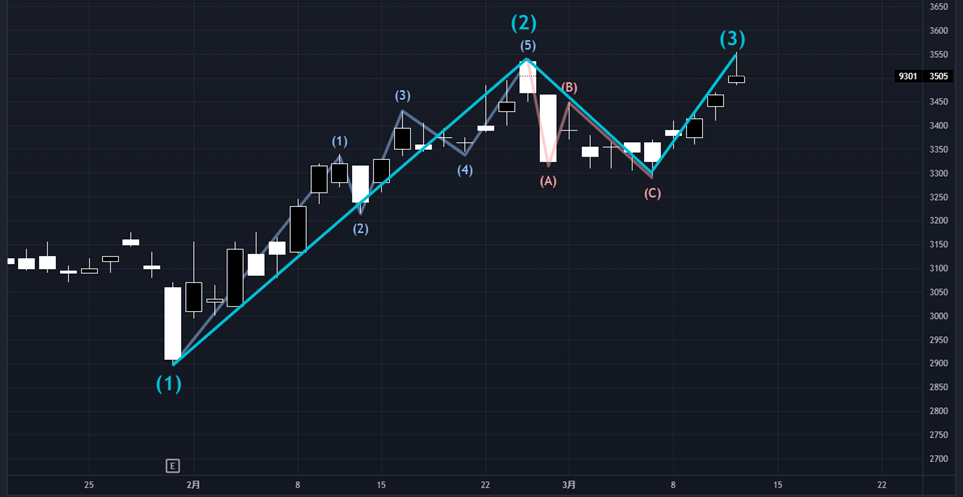1. ラルフ・ネルソン・エリオット
ラルフ・ネルソン・エリオットは、1871年~1948まで存命し、もともとは会計士でした。
病に倒れて仕事が続けられなくなったことを機会に、投資家への道を歩み始めています。
観察力に秀でた人物で、エリオット波動理論は、彼が見出したパターン認識に基づいたものといえます。
しかし、その波動は、相場にしか現れない特殊なものではなく、人間界のみならず、自然界に存在するさまざまな現象と、同一の性質をもつと強く確信していたようです。
エリオットの死後、その理論を発展させたフロストとプレクターは、1980年代の強気相場を見事に言い当てており、エリオット波動理論が他のテクニカル分析のように後追いでトレンドを確認するものではなく、未来を予見するための理論でもあることを主張するに足る成果をあげたといいます。
エリオット波動理論の適合範囲は株式にとどまらず、債券、為替、商品などすべての相場に及ぶとされています。
それはエリオットが見出した波動が、彼もまた追究した黄金分割やフィボナッチ数などとともに、自然界に存在する不思議な秩序を、人間の行動や心理にも当てはめたものだからといえるでしょう。