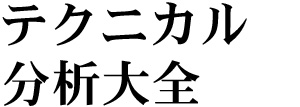1. 直近の高値更新を最も高得点とする順位付け
RCIは、スピアマンの順位相関係数を用いて、株価の上昇トレンドの強さを表そうとするテクニカル指標です。
英語では、Rank Correration Index といい、その頭文字を取ってRCIと呼びます。
計算に利用する参照期間は概ね10~20とされています。
下のチャートは週足で13週間を参照したRCIを描画しています。
▼日経225 (チャート:TradingView)

RCIは2つの側面から相場の順位づけを行い計算します。
● 時間 : 現在から遡って1位、2位、3位…と順位づけします
● 価格 : 値が高いものから順に1位、2位、3位…と順位づけします
時間は直近のものほど順位が高くなるように計算され、
価格は値が高いほど順位が高くなるという考え方です。
仮に参照期間を通じて、毎週値上がりしている相場であれば、時間、価格ともに最高の順位づけが行われてRCIの値は+100%になります。
逆に下がり続けた相場の場合は、最低の順位づけとなってRCIの値は-100%になります。
揉み合うような相場であれば、時間と価格との間に有意な相関が見当たらないため、RCIの値は0(ゼロ)に近づきます。
RCIは、相場の行き過ぎを察知するオシレータ系としての性質をもちながら、相場の方向性を探るトレンド系のテクニカル指標としての性質をも併せ持ちます。